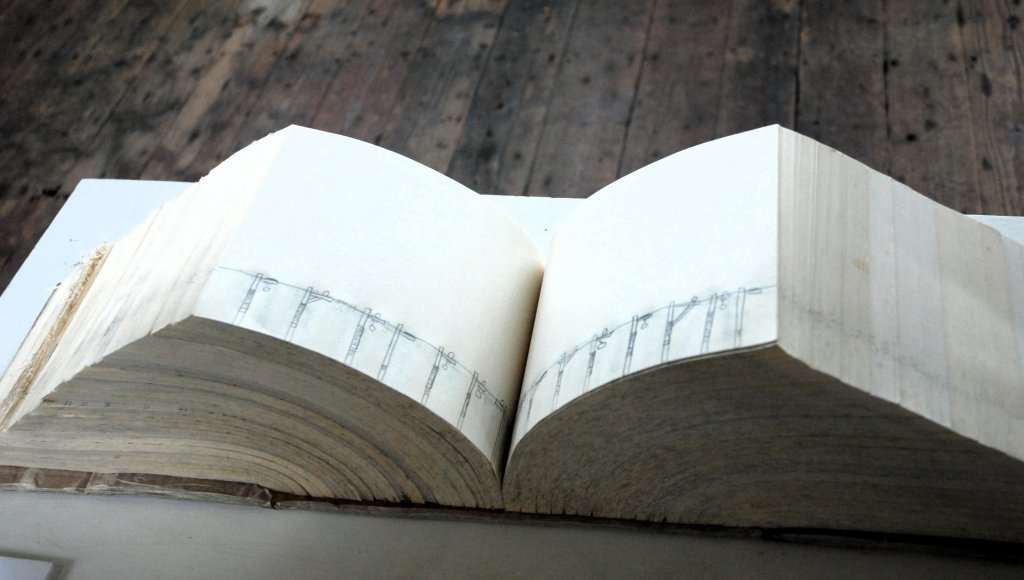角館の街並みを楽しむ

塀越しに通りから見えるように植える「見越しの松」は風情があるが、角館の場合、シダレザクラ、モミ、モミジ、松などの大木が「見越し」というスケールを超え、塀を圧倒している印象を受ける。城下町の面影を残す町並みにおいて通りの広さ、木の大きさが群を抜いている。シダレザクラが咲く時期、紅葉の時期は見事だと思うが、新緑の時期は森の中にいるような雰囲気だ。
巨木が多いため、通りを歩いていても武家屋敷の塀、門は見えるが、主屋の姿は伺えない。なおこの通りは、昭和51年という早い段階で、重要伝統的建造物群保存地区となっている。
重伝健に指定されている武家町(内町)は、1656年に佐竹北家が入部して以来400年、道路の幅から曲がり角ひとつまで街区形態がそのまま残っているのも特徴的である。江戸時代の通りとしてはかなり広い。

上中級武士の居住地であったことから町割は大きく、見学した青柳家は敷地が三千坪と広大。薬医門(青柳家の親戚が『解体新書』の附図を描いているが関係は?)と名付けられた門は趣がある。当時の門は家の格式を表し、藩の許しが必要だったとのことである。

母屋は約200年前、幕末の建物。寄棟茅葺屋根が往時をしのばせる。建物は簡素ながらも武家の威厳が漂う。大屋根の形状が茅葺のため、“枯れた”雰囲気が強く、入口にかかる懸魚が特徴的だ。城郭や寺社に用いられた懸魚は江戸中期以降、上級武家の屋敷にもみられるようになった。金属葺きの部分は石置き屋根だったと思われる。

内町の通りには、武家屋敷も残るが、建て替えられ店舗になっている屋敷跡もある。岩橋家は門をくぐると主屋を鑑賞できる。中級武士の典型的な間取りとのことであるが、入口がむくり屋根、懸魚がかかる点は青柳家と類似している。

続いて外町(とまち)と呼ばれる町人町へ。こちらは重伝建ではないが、豪商と寺社仏閣が多かった通りが町並みを維持しており、内町と比べ通りは狭いものの格式は十分高い。北の入り口には新潮社記念文学館がある。創設者佐藤義亮氏は角館出身で、近代文学に関する資料や原稿が展示されている。高校生の頃よく読んだ安部公房の文庫が新潮社のもので、以来新潮社には特別な思いがある。

外町は宿やギャラリーになっている建物もあるが、重厚さは内町に比べ遜色がない。寺社以外の建物は、時代は少しくだるものが多いようだ。

お昼近くになると観光客の姿も多くみられた。アジア系のインバウンドツーリストも多く訪れている。山桜の樹皮を用いる樺細工(かばざいく)を販売しているお店も多い。チラシと呼ばれる技法の作品は味わい深く、花入れがあったらほしいと思い尋ねてみたが、特注になるとのこと、いずれ検討したい。

苔むした石塔とシャクナゲが塀越しにみえる。風情と風格を兼ね備えた街並みだ。
増田(横手市)の街並みを楽しむ

14世紀に増田城が築かれ、1615年に一国一城令によって廃城となったが、17世紀の中ごろから久保田藩公認の定期市が始まり、流通拠点として栄えた。明治維新後も商業地として発展し、生糸、たばこで発展し、大正時代には吉乃鉱山の関係者で賑わい、昭和初期にかけて大いに繁栄した町である。

敷地は通りに沿って短冊形に割られ、間口は4~5間であるが、奥行きが50~70間と長い。悠に100mを超える敷地に、通りから主屋(ミセ、ブツマ、オエ、イマ)、ミズヤ(台所)、ウチグラが続く。ウチグラは主屋から続く鞘付き土蔵であり、土蔵が建物で覆われている。そこから、フロ・ベンジョ、ニワ、トグラ(外蔵、建物で覆われていない土蔵)、モンと続くのが一般的のようである。主屋からウチグラ(内蔵)まではトオリドマが配される。

特徴の一つがウチグラ(内蔵:鞘付土蔵)である。正面と背面には掛子塗の扉、磨きこまれた黒漆喰は色褪せていない。風の強い本地では火災が多く発生するため財産を守る土蔵は必須であった。しかし豪雪地帯でもあり、漆喰の壁は雨雪に弱い。そこで土蔵をつくり、木造の鞘で守っているのだ。

主屋は切妻妻入の二階建て。一間程度の下屋出しである。二階は庇を張り出し、内縁としている。ケラバが大きく出ており、化粧梁を重ね、壁面から突出する梁首(装飾)が力強い。

見学させていただいた佐藤又六家は、主屋自体もウチグラになっている珍しいタイプ。当時の主が、延焼を食い止める防護壁の役割にもなるため、主屋も鞘付き土蔵にしたとのことである。仏間の2階には通常の民家ではみられない大きさの神棚が設置されており手の込んだ斗栱が目を引く。

これだけの建築物を維持していくのは大変であり、すでに個人の手をはなれているものもあるが、様々な形態で活用されているケースも多く、生活者の息遣いが聞こえてくる重伝健地区であるといえる。佐藤又六家の当主に内部を案内頂いたが、増田の繫栄に誇りを持っていることが伝わってきた。建物とともに、ここで暮らす人、増田への思いが継承されることを願う。
番外編 秋田のB級グルメ 横手やきそば
増田の街並みを見に行くついでに、横手に寄って「横手やきそば」を頂いた。年に一度「横手やきそば四天王決定戦」(現、横手やきそばフェスティバル)を開催しており、トップ10が推奨店、トップ4が四天王を名乗ることができる。伺った「藤春食堂」は12年連続四天王受賞中である。外観は、ザ・昭和の食堂だ。

午後1時15分ごろについた。待っている人は一組。なんとか入れそうだ。内容は分からないまま特製をお願いする。

目玉焼の黄身を絡めながら食べるのがコツのようである。ソースはやさしい味。足りないようならテーブルのソースをかけるのが流儀らしい。麺は太めだがやわらかい。すっごくスペシャルな焼きそばではなく、身近にあると週に1度はたべたくなる、そんな味である。遠方からわざわざというよりも、生活に寄り添ってくれる味。そんなお店が評価されているのも、横手やきそばのいいところだと思う。
(米田)